幅広い年代に愛され続けているPOTATO!そう、じゃがいも。
じゃがいもは、ベランダのプランターでも育てることができるとあって、家庭菜園でも人気の根菜です。
幅広く料理に使えることでも人気のじゃがいもですが、見た目はキレイなのに、切ったら中から茶色の模様がでてきたこと、ありませんか?
茶色だけでなく、じゃがいもの中が黒かったり、空洞だったりした経験がある人は多いはず。

じゃがいもの中が茶色いものは、危ないので食べない方が良いのですが、茶色い部分を取り除けば食べられるものもあります。
こちらでは、じゃがいもの緑や、赤い色についても解説していますので、じゃがいもを詳しく知って、安全でおいしい料理や家庭菜園に役立てましょう♪
目次
じゃがいもの中が茶色い時は取り除く必要がある
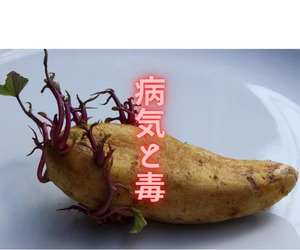
料理しようとじゃがいもの皮をむいて、まな板にのせて、トン!
切った瞬間、キレイに見えたじゃがいもの中が茶色くて、嫌な気持ちになったこと、あなたにもありますよね?
あの茶色いじゃがいもは食べられるのか、状態別に解説していきたいと思います。
皮の近くに茶色く輪のあるじゃがいも
じゃがいもの中でも、皮の近くに輪のように茶色い線が入っているもの。
茶色い輪の原因は「輪腐病(わぐされびょう)」という、植物病原細菌による、じゃがいもの病気の可能性が考えられます。
輪腐病(わぐされびょう)の植物病原細菌感染は、種芋を植える時にひきおこる、じゃがいもの病気です。

茶色い輪のじゃがいもは食べられますが、茶色い部分は味も悪く、原因が細菌によるものなので、取り除いてください。
茶色い輪ごと、皮を厚めにむいてしまえば、中は食べても問題ありません。
輪腐病(わぐされびょう)は、種芋を植える前の切断時に、種芋が病原菌に感染してしまうことが原因です。
感染した種芋からできるじゃがいもは、感染して育ち、中に茶色い輪ができてしまうんですね。
家庭菜園をする方は、種芋を切断するときに、ナイフや種芋を消毒することで防ぐことができます。中心近くに茶色のシミがあるじゃがいも
じゃがいもの中の方に、茶色や淡い茶色がかったシミのようなものを見かけたりしますよね。
褐色心腐病(かっしょくしんくされびょう)といって、栽培中の水分不足が原因で、中心部分が枯死しているじゃがいもです。

枯死した部分は、加熱しても柔らかくなることはありません。

中心の茶色い部分は加熱しても硬くて食べられませんが、取り除けばシミのない部分は食べられます。
加熱前にしっかりと取り除きましょう。
中心近くに黒いシミがあるじゃがいも
じゃがいもの中が茶色というより、黒っぽいものがありますよね。
じゃがいもの中心部が、濃い茶色や黒っぽいものは、黒色心腐病(こくしょくしんくされびょう)のじゃがいもです。
褐色心腐病(かっしょくしんくされびょう)と似ていますが、もっと色の濃い黒っぽいシミが中心部にあるのが特徴です。

じゃがいもは日持ちしますが、あまり長く置いておかず、早めに消費した方が良さそうです。
高温多湿の場所は避け、換気のよい涼しい場所で保管することで防げます。
皮がかさぶたのようにデコボコしたじゃがいも
じゃがいもの中ではなく、皮の部分がガサガサとひび割れて、茶色い斑点やかさぶたのようになったじゃがいも。
じゃがいもの皮に異常がある場合は、そうか病という病気の可能性が高く、斑点や網目状に亀裂が入っているのが特徴です。

そうか病は、土壌に生息している菌に感染してできる、じゃがいもの皮膚病みたいな病気です。
皮を厚くむけば、中は問題なく食べられるので、皮に異常がある場合は、皮を厚くむきましょう。
味にも特に変化はないので、厚くむくことで小さくはなりますが、捨てるのはもったいないですよね。
種芋を植える前に、土壌の殺菌剤を使用し、消毒した種芋を植えることで、かなり防げます。
そうか病になりにくい品種を選んだり、土壌pHを5.5以下に保つことでも防げます。
【緑色は危険度MAX】食べないで!!
じゃがいもの芽には、ソラニンなどの天然毒素が含まれていて危険なことは、知っている方も多いと思います。
でも、芽が出ていないじゃがいもの、皮が緑がかったものって、時々見かけませんか?
皮が緑のじゃがいもや、皮をむいても中まで緑っぽいじゃがいもだったら、要注意です!

じゃがいもの緑色には、芽にある毒素と同じ、ソラニンやチャコニンといった、天然毒素が含まれています。
皮を厚めにむいて、中が白ければ食べても大丈夫ですが、中まで緑っぽい色をしていたら、迷わず捨てましょう!
加熱しても毒性がなくなることはないので、絶対に口にせず、緑色のじゃがいもは捨てるか、発芽させ種芋に。
食べてしまうと、主に次のような食中毒症状を引き起こします。
- 吐き気
- 嘔吐
- 下痢
- 頭痛
- めまい
さらに、死亡例もある「毒」だということを覚えておきましょう。
食べてしまった時は、家庭でできる対処法はないので、すぐに病院に行ってください!
じゃがいもは、とても身近で人気がある根菜ですが、毒性が強いので注意が必要です。
緑色のじゃがいもは、主に家庭菜園で作られたものに多いので、栽培している方は注意しましょう。
じゃがいもは、大根のように土中深く、下向きには育たず、横に横にと根を伸ばし、育っていきます。
横に伸びることで、じゃがいもが土から出てしまった部分に、日光が当たり、光合成をして「ソラニン」を生成してしまいます。
種芋の芽が育ってきたら、苗にややかぶせるように土を追加して、光合成を阻止することが、何より大切です。
じゃがいもの芽の処理
じゃがいもの芽には「ソラニン」「チャコニン」といった天然毒素が多く含まれていることが有名です。
うっかり発芽させてしまったじゃがいもでも、芽を正しく取り除くことで、食べることが可能です。

芽を取れば大丈夫だからと言って、芽だけをポロリと取るのは危険です!
芽だけでなく、芽周辺のじゃがいもの中にも毒があるので、芽の周りの皮を厚くむくか、えぐり取る必要があります。
この時、皮をむいても緑色をしているようなら、緑がなくなるまでそぎ落とすことも忘れずに!
除菌された刃物で、芽のあるじゃがいもを半分に切り、植えてみましょう。
ただし、保存状態が悪かったり、発芽した状態が悪いものは汚染されていて、病気の原因になることもあります。
種芋として利用する際は、状態の良いものを消毒してから使いましょう。
じゃがいもの中に茶色い空洞がある?取り除こう!
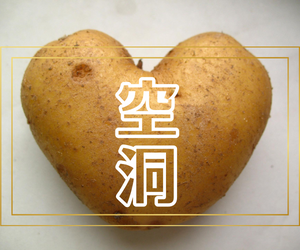
じゃがいもの中に茶色い空洞や、黒い空洞、特に色のない空洞などを見たことはありませんか?
ここでは、じゃがいもの「空洞」について説明していきたいと思います。
じゃがいもの中に茶色い空洞がある
じゃがいもの中に茶色い空洞があるものは、褐色心腐病(かっしょくしんくされびょう)が原因で枯死した部分が広がった可能性があります。

じゃがいもの中が茶色い空洞だけでなく、黒っぽくなっている時は、黒色心腐病(こくしょくしんくされびょう)による枯死の広がりかも知れません。

その他にも、空洞病(くうどうびょう)という病気の場合もあります。
空洞病の場合、じゃがいもの中が茶色く空洞になっていることに加え、コルク化して固くなっていることも。
じゃがいもの中に茶色い空洞があるとき、または色のついた空洞は、取り除いてから調理してください。
じゃがいもの病気の部分を食べるのは、気分的にも良くないものです。
じゃがいもの中に黒い空洞がある
じゃがいもの中に茶色い空洞があるものや、黒い空洞があるものの中には、病気由来ではないものもあります。
成長過程で出来た空洞に、カビなどが生えてしまって黒くなっているものです。
じゃがいもの中の茶色い空洞や黒い空洞のなかには、穴が外部にまで広がっているものもあります。

カビは人間にとって毒になることもあるので、空洞とその周辺は取り除いて食べるようにしてください。
じゃがいもの中に白い空洞がある
ここまでで、じゃがいもの中に茶色い空洞や、黒い空洞がある場合は取り除くことが大切だとわかりました。
では、色のついていないキレイな空洞の場合はどうなのでしょう?

毒性はありませんが、空洞部分は固く、食感も味も良くありませんので、取り除いて食べましょう。
じゃがいもの成長過程で大きくなるときに、中心部分へのでんぷん質の供給が間に合わずにできてしまうものです。
目に見えなくても、カビの胞子などが付着している可能性もないとは言えないので、取り除いてくださいね。

でんぷんが不足してしまう原因は、じゃがいもが急激に成長してしまったため。
急激な成長の原因は、気温の上昇と多肥によるものが多いと考えられます。
家庭菜園では、適度な肥料にとどめ、肥料をやりすぎないよう心がけ、敷きワラをかぶせることで暑さから守ってあげると防げます。
じゃがいもの中が赤いものは低温障害の可能性!!

最近は、サツマイモのように、じゃがいもの中が赤い品種も増えてきましたよね。
茶色のじゃがいも以外にも、赤いじゃがいもについても触れておきましょう。

普通のじゃがいもの中が赤い場合
普通のじゃがいもの中が赤いものを、あなたは見たことがありますか?
赤い品種ならいいのですが、普通の男爵やメークインを切って、ピンクだったり、赤い色がついた部分があったら驚きますよね。

じゃがいもが低温障害をおこすのは、育つ過程で温度が低く寒い時があった場合。
他には、保存している時に寒い場所で保管していた場合にも、低温障害をおこします。
じゃがいもの芽の周辺が赤いものは危険ですので、しっかりと取り除いてくださいね!

赤い色以外にも、表面の凹凸やシワが寄るなどといった症状が出ることも。
敷きワラや、園芸用の黒いビニールなどを敷くことで対策は可能です。
ベランダのプランターの場合は、寒すぎる時だけ室内に入れても良いかも知れませんね。
温度が高すぎても低すぎてもダメなじゃがいもですが、考えすぎず育ててみるのも面白いと思います。
じゃがいもの中が赤い品種
最近ではじゃがいもの品種も豊富で、赤い皮を持つものから、中の赤いものまであります。
中まで赤いじゃがいもとは対照的に、皮が赤く中が真っ白な品種「レッドカリマス」といったじゃがいももあるんですよ。
皮は赤いのに、中は濃い黄色のじゃがいもなんかもありますよね。

皮も赤く、じゃがいもの中まで赤いのは「ドラゴンレッド」と「ノーザンルビー」の2品種が有名ですね。
じゃがいもの赤い色の正体はいったいなんなのでしょう?

ポリフェノールは抗酸化作用が強く、生活習慣病の予防にも良いといわれています。
じゃがいもには驚くほど多くの種類があるので、料理によってじゃがいもを使い分けると料理の腕が上がったように感じることでしょう。
まとめ
- じゃがいもの中の茶色や黒の変色は、取り除くことで、変色のない部分を食べることができる。
- じゃがいもの芽や、皮が緑のものは毒性が強く危険なので、芽や周り、緑の部分は食べない。
- じゃがいもの空洞は色の有無にかかわらず、取り除くことで、まわりに残った部分は食べられる。
- 家庭菜園では、病気や空洞に気を付け、毒素の生成を防ぐため、じゃがいもを日に当てない。
- じゃがいもの中の赤い色は、成長過程や保存時の低温障害によるもので、食べても問題はない。
- じゃがいもの赤い品種の色の正体はポリフェノールという天然由来の色素で、毒性はない。
じゃがいもの中が茶色くても、取ってしまえば安全に食べられるんですね!
プランターでじゃがいもを育てるのも、なかなか楽しそうです♪

